夏になったら本気出すと宣言した通り、夏になったので本気出して来ました(笑)
マツダ2に乗り始めてしばらく経ちますが、慣れない前輪駆動の車に加え、どう扱えば良いのかわからないトーションビームの足回りに悩まされていましたが、ようやく操り方を理解してきました!
これまでにFFの動きを観察したりアドバイスをもらったり、色々とイメージしながら試行錯誤を繰り返していましたが、時間をかけて試している内に気付いた事も多い。
今日は先日予告した記録更新を宣言通りに達成できたのか、結果はどうだったのかと言う報告に合わせて、今まで見聞きした事の復習と私の見解を綴ってみます。
マツダ2のセッティング考察の続編として見て頂ければ良いかと。
上手な方には鼻で笑われてしまう様な内容かもしれませんが、FFが苦手な方や初級者さんにとって何かヒントにでもなれば幸いです。
■まずは結果報告とFFの特性に関する結論
まずは好感触だった先日のリセッティングで、記録更新の宣言と、可能ならデミオの車種別コースレコードを抜くとお伝えした結果について。
ぶっつけ本番となってしまったので様子見のつもりでしたが、ウォーミングアップ後の僅か1周目にしてあっさり両方達成しちゃいました(笑)
2周目には35秒1の記録でデミオの車種別レコードに0.7秒差を付けましたが、かなり余裕を残した走りなので少なくともあと0.3秒は普通にイケます。事前に、次回は34秒台と予告をしておきます(笑)

手応えを感じて2本目のアタックではペースを上げて臨んだものの、残念ながら計測器の誤作動で記録が残らなかったため、予想通り34秒台に届いたのかどうかは不明ですが、運も実力の内と言いますし、この日は35秒止まりの流れだったのかもしれませんね。。。
買ってきたノーマル車両に最小限のチューニングだけで35秒前半~34秒台が狙える事を示せたなら、軽やコンパクトカーなど低予算で楽しみたいと言う層に希望を与える事にも繋がるので、何としても34秒台の目標はクリアするとお約束します!
マツダ2に乗り始めた当初は元々普段の足のつもりで買った車だった事もありますが、1.5LのNAエンジンで100馬力そこらのコンパクトカーなので期待などしていないし、周りも大して興味を示していない様子。
一本クヌギで他の同クラスの車両を見ると、スペックで優位なシビックTypeR(EK)やスイフトスポーツでは平均を上回る記録も見られるが全体では38~37秒辺りが多く、ジムカーナ選手でもそれ相応のセッティングをして36秒前半~35秒後半と言った感じなので、36秒台で走れるようになれば並み程度にFFも乗れるようになったと思っていいかな?くらいに考えていました。
…が、この時もあっさりと36秒5が出ちゃったし、更にこれ以前にNAのスイフトスポーツをお借りして走らせた時も、不慣れなFFで大雑把に走ったにも拘らずあっさりと35秒3なんて記録が出ちゃったのですが、それは私が何でも器用に乗りこなせる凄腕ドライバーだからだ!…なんて事ではなく、実はここに”ある秘密”が隠されている。
秘密なんて言うとちょっと大袈裟ですが、私が思うに実は”FFとFRの走らせ方に大きな違いはない”と言う結論です。
駆動抵抗の掛かる車軸が違うし足回りの構造なども多少の影響はあると思いますが、どちらかと言うとフィーリングの話であって、極端には違いがあるのはあくまでもコーナーで舵を入れてアクセルを踏み込んだ時の挙動だけで、惰性で走っている分には変わらない。(アクセルオンの挙動が違えば実際には”大違い”だが、これについては後述する)
その他は強いて言うなら構造上バランスが比較的良いFRに対して、FFはリアが極端に軽くなり易いと言う違いはありますが、これについては重量バランスを見越して足のセッティングを考えれば良いだけなので、どう動かしたいのか?と言った理想をイメージする事が重要になってくる。
単に気合と根性だけで走らせたところで、まぐれで一発好記録が出る可能性はあっても再現性が低いのはFFに限った話ではない。
■FFのセッティングに於ける最大の愚行
FFの車に挑戦して、コツが掴めない内は多くのアドバイスを頂きましたが、実際に走って確かめていると中には明らかに間違った方向だと感じた事も含まれる。
私なんかより遥かにFF車の運転歴が長い大先輩の意見にケチを付けているように思われるかもしれないが、事実として”そう感じた”アドバイスの中でも、最大の愚行と思われるのは”リアの限界を下げる”と言うセッティングである。

どの程度なのか?加減の問題もあると思いますし、もしかすると有効なカテゴリもあるのかもしれないが、FFはアンダーが強く曲がり難いと感じる、またはそう思っている人が多い様で、その解決策として極端にはフロントに対してリアのトレッドを狭くする(実際、メーカー標準でリアの方がトレッドの狭い車は多い)とか、リアタイヤを細くするorグリップの低いタイヤを履かせると言った方法を取り”リアを滑らせる”事で曲がり易くしようとする狙いである。
意図的にスリップアングルを調整して”向きを変え易くする”と言う考えとしては間違っていないと思いますが、その方法が”リアを滑り易くする”と言うのは大きな間違いだと思います。
勢い良くコーナーへ突っ込んで行っても狙い通り向きはコントロールしやすいですが、その先で踏めなくなるか、勢いに任せてアクセルを踏み込んでも思う様に前には進まず、体感ほど速くはないと言う結果になる。
リアが滑ってもFFはフロントで引っ張って走れば良いなんて言う人もいますが、リアが滑る事によるロスは想像以上に大きく、滑ったリアをフロントで引っ張っている気になっていても、現実にはフロント側で生じたアンダーがリアのオーバーを相殺して見掛け上の姿勢が安定いるだけで、車が効率良く前に進んでいるわけではない。
ここに機械式デフなどを組み合わせると尚更で、フロントが抵抗になって”曲がり難い=FFは曲がらない”と言うイメージを決定付ける要因と成り得るばかりか、本来の目的である旋回速度が稼げないまま立ち上がりのトラクションだけでタイムを稼ぐ”デフに甘えた走り”となり易い。
前項でも触れましたが、FF車の多くはFR車に比べて極端にリアが軽い傾向にあり、特に軽自動車やコンパクトカーに至っては本格的なスポーツカーに比べて足回りの構造もチープ寄りで限界が高いとは言えない物も多い。
ブレーキングで意図も簡単にリアの荷重は抜けるし、何もしなくても慣性の影響を受け易く、むしろアンダーよりオーバーの挙動が出る可能性の方が高いと考えている。(軽い分、止めるのも容易いが)
一定の領域を超えてくると、上手くオーバーの挙動を制御してやらないと旋回速度を上げられなくなるので、速く走るためにはFFでもリアのグリップは重要だ。
これについては、コースを2~3周もしていればすぐに気が付く事なので長期的に悩まされる心配はなかったが。。。
■”リアで曲げる”とどうなるのか?
トレッド幅やタイヤサイズでグリップバランスを崩して向きを変え易くするのではなく、そもそも滑り易い、止めるのも容易いリアを”運転操作”でコントロールして走る方法はどうだろうか?

実のところ、FFに乗り始めた直後から既に”FFは曲がり難い”とは全く思わなかったのですが、安定感を出すためにどアンダー方向にセッティングしておいて、必要な時はブレーキ操作でリアの荷重を抜いて振り回す走り方を試してみる。
FFはコーナーでリアが僅かに流れるくらいが速いなんて話も聞きますが、これはたぶん慣性でズルズルと動き出すような限界付近の走りが出来ている時の話ですよね。
私がやっているのは所謂ブレーキングによるドリフトに近い操作で、ターンインで僅かに滑らせて必要なアングルを確保出来たら、後はその先の軌道が容易に予測できるはずなのでアクセルでスライドを止めに入る。
これは一瞬とは言え意図的に姿勢を乱して走っているに過ぎないので、それなら最初から素直にグリップで向きを変えた方が速いんじゃないだろうか?その方が、突っ込み気味に進入する事で生じるリスクも抑えられる。
実際にこの走り方を試していると、FFなのにリアの外側だけタイヤが減るので、コーナーではフロントタイヤに余裕を残しまくっている状態である。
フロントに余裕があるなら、もっとフロント側に頼る割合を増して四輪を効率よく使うべきだだろう。
確かにフロントに頼らず舵を半分リアに任せておけば、加速側に使える余裕ができますが、トータルグリップを上手く活かせば旋回速度をもっと上げられるはず。
なので、この走り方も違う。
■FFの足回りセッティングをどう考えるか
FFの足回りをセッティングする上でどんな動きを求めるのか、どんな狙いがあるのか考えながら進めていくと、やはり一番優先的に考えるのは駆動輪となるフロントの接地性と答える人は多い。

過去にも何度か同じ話をしていますが、フロントの接地を促す方法として、いくつかの手段が思い浮かぶのではないでしょうか。
例えば、車高調で前後のバランスを予め前下がりの前傾姿勢にしておいて、常にフロントに荷重が乗り易い状態を保っておく方法。
この方法では旋回中でも舵は利き易いがリアの荷重が抜け易いとも言えるので、コーナー進入時にオーバーが出易かったり、ブレーキング時に姿勢が不安定になる可能性も出てくる。
他には、フロントのスプリングを柔らかくしたり減衰を下げておく事で、コーナー進入時に荷重が乗り易くしたり、アクセルオンでフロントは浮き易いが、その分伸びストロークや伸びの速さで接地性を確保する方法。
この方法ではターンインでハンドルを切った時の反応も速く曲がり易いが、S字コーナーやスラロームなどの切り返しが鈍くなったりする。
リア側で調整する方法には、リアのスプリングを固くする事で沈み難くしてフロントの荷重がリアに移るのを抑えると言った方法もあるが、この方法だと立ち上がりのトラクション抜け防止には有効だが旋回中にリアが滑り易いと言うデメリットも。
いずれの方法も加減やバランスを取って調整するべきなので、それぞれの特徴を見ながらどう配分するかと言う事になりますが、ここに多くの人が嵌っている罠があるように思えて仕方がない。
FF乗りの先輩方から色々なアドバイスを貰っていると、アドバイスをくれる人の多くが上記の通り”フロント”をどうにかしようと言う話しかしないのだ(笑)
全てフロント頼りでは速く走る事が難しいと言う事については前項までに触れている通り、もっとリアを積極的に使う走りをイメージしてセッティングしたい。
■トーションビームのインリフトは防げない?

吊るしの車高調はやけにリアが滑り易いセッティングに感じる。
これについては全ての車高調を試したわけではない…と言うより、当然試せるわけがないので、あくまでも私が使用しているクスコのSPORT_Rに限定した話になりますが、吊るしの状態でフロントが12kgf/mm、リアは10kgf/mmとかなりのハイレートにセットされた状態で販売されている。
さすがに固過ぎる印象を受けたのでリアは8kgf/mmに下げてオーダーしたが、それでも異常なほど固いと感じるくらいです。
SPORT_Rはテストドライバーがサーキット走行でテストして導き出したセッティングで販売されていると謳っているが、プロドライバーでさえリアの流れるFFの方が良いと感じているのだろうか?
それとも、とどのつまり商売なので、市場のニーズに合わせているだけだろうか?
FFは曲がり難いと考える人は多いので、コーナーで容易に”向きが変わる=曲がり易い”と誤認して、良い足と考えるユーザーも少なくはないはず。
何故リアが流れると思うのかと言うと、何度も言うがリアは極端に軽い。
リアのレートが高いとそもそもロールし難い事に加え、フロントのレートが高いとフロントのロール剛性につられてリアが更にロールし難くなる。
つまり、リアタイヤに荷重が乗り難くなるので、面圧は下がりグリップが発揮できずに滑り出す。
対してフロントにはエンジンと言う重りが乗っかっているので、不十分なロールでも一定のグリップを確保したままオーバーステアの挙動に移行する…と考えていたのですが、現実にはそうはならなかった。

走る前から予想していた通りリアが滑る事に違いはないのですが、思っていた動きと違った方向で問題が発生する事に。
これについては過去にも触れていますが、ロールはするがハイレートなスプリングを使用する事で伸び側のストロークが不足して内側の車輪が浮き上がると言う症状(インリフト)です。
これはトーションビームの特性も影響していますが、一番の原因はセパレート式のサスペンションとなる事で、ハイレートのスプリングを組むと車高を下げるためにスプリングのレングスを短くせざるを得ない。
スプリングを短くするとショックの全長も縮めないとスプリングの遊びを防げないので、結果として極端に有効ストロークの短い短足セッティングに仕上がる。
この状態で旋回速度を上げていくと、写真の通りリア側のインリフトが起きて、リアは外側のグリップだけに頼る事になるので滑り易いと言うわけ。
このセッティングで走っているとやはりリアタイヤの外側摩耗が目立つので、最初はキャンバー不足を疑って社外品のキャンバープレートを取り付けようかと考えたくらいですが、写真を見ればキャンバーが原因ではない事がよくわかりますね(笑)
もちろんキャンバープレートは却下して、もっとシンプルでスマートな方法を考えましょう。
このインリフトをトーションビーム式サスペンションの構造上、仕方がない、当たり前と言う意見も頂き、その場では相槌を打ちましたが、私はそうは思いませんでした。
構造上インリフトし易いのは事実ですが、ノーマルのサスペンションでは簡単に起きない事なので、セッティングを見直せば防げる、または緩和出来る可能性は十分にあると考えたわけです。
トーションビームの構造図を眺めながら動きをイメージしてみたりと長い事頭を抱えましたが、冷静に考えるとそんなに難しく考える必要はない事に気付く。
ノーマルが何故良く伸びるのか考えれば答えは明白で、ギンギンにプリロードこそ掛けてあるものの、長くて低レートなスプリングを使用しているからだ。
そもそも固すぎるリアが原因となるわけですから、実際にリアの動きを感じながら許容できるギリギリ手前まで少しずつレートを下げていって”オイシイ所”を見付けてやれば良いと言う事になる。
ただし、リアのインリフトを抑えて安定させたら本当に良くなるのかどうかは別の話である。
これで世間のイメージ通り曲がり難いと感じる様であれば、私の考えは間違っていて、FFはリアの滑り易いセッティングが良いと言う意見を認める事になってしまう。
■覚醒
遂に眠っていたマツダ2の力が目覚める時が来た!
それは意外にも、振り出しに戻る事で答えに近付いた形となりました。
FRとFFは違うと言う先入観から、FFはこう動かすべき、こうセッティングするべき、とあれこれ意識して見当違いな方向へ向かっていただけで、FFに乗り始めた直後の様に”違いを意識せず”ハンドルやシートから得られるインフォメーションを頼りに”感じるままに走らせる”と言う、はっきり言って”同じ事”をするだけで良かったのだと言う事に気付きました。
要するに、完璧ではないにしても”初めからFFをそれなりに扱えていた”って事である。
冒頭でも言った通りアクセルを踏み込んだ時の挙動は異なりますが、得られる情報を処理して対応、または予測して操作するのはFFもFRも同じ。
同じ駆動方式であっても、車が違えば挙動も違うので、それに合わせた運転をするのと同じ事だと思う。
何をしたらどう動くのか感覚を掴んで挙動に慣れてきたら、後は頭の中でイメージした理想の動きに近付けるように操作の加減やタイミングを調整してやればいい。

例えば、曲がり難いと言う人が多いFFのコーナーリングのコツ…的なものがあるとすれば、余計な事はしない。これに尽きる。
何度も言いますが、私が思うに大きな”違いがあるのは舵を入れてアクセルを踏み込んだ時”の挙動だけ。
言い換えれば、アクセルオフからブレーキング、ハンドルを切り込んで向きが変わり始めるまでの”ターンインの区間”は、極短時間の話ではあるがFFもFRも”駆動を掛けずに惰性でタイヤを転がしている”ので大きな違いはない。
この時、基本に徹して余計な事をしていなければ、素直に曲がってくれなきゃおかしいわけだ。(見当違いなセッティングだったり、デフが効き過ぎていると言う場合は別ですが)
普通に意見するだけでは単なる”偏見”と思われるかもしれませんが、私もお粗末ながら20年以上クヌギランナーと言う走行会イベントの主催を続けてきて、相当な台数の走りを観察してきたから”傾向”として言える事があるのですが、どう言うわけかFF車に乗っている方の多くは…と言うより、ざっくりと見て7~8割くらいの人は平然と突っ込み過ぎている様子が見られます(笑)
それはたぶん、FRでも曲がんないですよって、いや、ホントに(笑)
もし…、もし、ですけど…
曲がらない理由がドライバーの操作にあるとしたら、いつもよりワンテンポ速く減速を開始するなど”控え目な突っ込み”を試してみてください。
話を戻しますが、動きをイメージしてセッティングしたり操作したりと言うのは、まずは自分がどう動かすのが理想なのかとある程度考えをまとめておく必要がある。
まあ、私も上手いわけではないので偉そうな事は言えませんが、車の動きを理解して、理想の動きを具現化出来るようにイメージをすると言うのは大切な事だと思います。
これまでに話をしてきた、リアを動かして曲げたいと考えている人なら、そう動かすセッティングや操作になるのは当然の事だと思いますが、それができるノウハウをお持ちなら、反対にリアを安定させてフロントがインに切り込んで行くようなセッティングも、足の動きや荷重の乗せ方をしっかり”イメージすれば可能”なはずです。

私のロードスターは試しに乗った何人かが曲がらないと言ったのですが、それはたぶんリアを動かして曲げようとしているからで、私が想定したセッティングとは逆の操作をしているからだと思います。
私がイメージしたのはあくまでも、リアは安定方向で、ターンインで鼻先をスムーズに転がしたら、後はアクセルを入れて”フロントをインに押し込む”動きである。
そして今回、私がマツダ2に施したセッティングのイメージは、リアは安定方向で、ターンインで鼻先をスムーズに転がしたら、後はアクセルを入れて”フロントをインに引き込む”動き。
前回のクヌギランナーで2本目のアタック後に、ある方が”ヘアピンをロードスターみたいにクイックに曲がってる”と言っていましたが、どうしてそう見えるのかと言うと、やはり”フロントを動かす”から鋭い小回りをする動きに見えるわけですよね。
それってターンインまでスムーズに完了したら、後はアクセルを入れると勝手にフロントがぐいぐいとインに向かってくれるわけ?
だったら同じじゃね?って思ったかもしれないが、この部分が”FFとFR”の違いを意識してセッティングすべきポイントだと考えています。
だって、駆動輪が違うんだから。。。
特に機械式デフを使用した場合など、アクセルを入れると駆動輪は左右が直結に近付いて、同時に強い駆動抵抗を生じるので曲がり難くなる。
なので、あえて不必要な荷重を抜いてやり、駆動して欲しい”駆動輪の外側”が効率よく回ってくれる事をイメージしてセッティングしてやる。
もちろん車によって差はあるしドライバー毎にの運転のクセも違うので、一言に”これだ!”とは言えませんが、方向性としては”駆動輪の伸び減衰強め”が私の回答です。
ガチガチにするのは話は別ですよ?(笑) あくまでも”強め”である。
実際の伸びの差は0.1秒未満と言った一瞬の差しかないと思いますが、現実にヘアピンコーナーなどでターンインの後、立ち上がりに向けた準備までに要する時間は0.1秒と掛からない場合が多いはず。
まさか!と思うかもしれないけど、私に限らずみなさんこの一瞬の間に無意識でもあらゆる操作をしているはずですよ。
実際の動きとして何が起こっているのかは定かではありませんが、感覚的に伝わって来る一瞬の伸び遅れを見逃さずアクセルを入れて、イン側の抵抗が発生する前にコーナーリングを完了させる”イメージ”で操作している。
そして、それを実現するために車高調の減衰を調整してサスペンションの伸縮スピードを加減しているわけです。
そしてもう一つ、今回は機械式デフを装備して初走行となりましたが、経験年数だけは長いのでヘタクソなりにもデフの使い方は心得ています。

実は前回のクヌギランナーで、スペックの近い田辺さんのヤリスと勝負だ!なんて約束をしていました。
こちらのヤリスも同じタイミングで機械式デフを装備しましたし、オープンデフの時点でお互い36秒半くらいがベストタイムとなっているので今回も近いタイムで接戦となる事を予想していたのですが、意外な事に田辺さんは記録を伸ばせませんでした。
これは敗者を晒し者にしているわけではなくて、ですね(笑)
何が決定的な差になっているのか、読者のみなさんも含めてお伝えしたいのです。
私と田辺さんの基本的な運転スキルに大きな差はなく、どちらが勝っても不思議ではないと考えていますが、では何故私が大きくリードしたのかと言うと、機械式デフの使い方を理解しているかどうかの差、それだけだと思います。
つまり…次回か、その次か、慣れてくればあっと言う間に追い上げてくるはずです。
結構勘違いしている人も多いですが、先程言った”デフに甘えた走り”は、あくまでも”おまけ”の部分に過ぎない事は10年以上前からず~~~~~っとお伝えしてますよねえ??
ちゃんと過去の記事も読んでくれてます??(笑)
機械式デフを入れると立ち上がりのトラクションが~なんて部分など、本来の機械式デフの目的から考えるとどーでも良い事なんです。
一番の目的は”旋回速度を上げる事”なので、旋回速度を上げられる様な操作をしてやらないとパーツの機能を活かせないわけですよ。
だからと言って、やたらと気合だけで突っ込んで行けば良いわけではないが、入口から出口まで、一定の強い旋回Gをキープして曲がる様に意識してみてください。










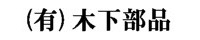
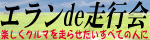



初めてコメント致します
神奈川県から熊本県へと移住した12年前、「アシ車としてNBロドスタNR-Aでも購入するかねえ」とマツダ公式中古車サイトを閲覧中、偶々目に留まったDYデミオスポルト(オレンジ色の前期型・5MT)に妙に惹かれ、ほんの繋ぎとして購入しました
ホンダ党の自分にとっては初のマツダ車だったものの、意外なほどにウマが合い、メンテやカスタマイズを重ねつつこれまで乗り続けてきましたが、つい最近になって車体骨格部の看過し難い経年劣化が判明し、更なる大枚を叩いての維持or乗り換えの二択を迫られた次第です
諸々考えておりましたが、こちらのサイトを閲覧した事でマツダ2の15MBへの乗り換えを決断し、面倒を診て頂いているマツダディーラーにて先週本契約を交わしました
約2ヶ月の納車待ちですが、15MBへと乗り換えた暁にはいろいろと参考に致します
最終的に背中を押して頂き、有難うございました🤗
購入時の参考にして頂き光栄です。
DJ型はDY型に比べて車重も軽くパワーもあるので、より面白くなりそうですね!
私も当初は普段乗りの足として購入しただけで期待はしていなかったのですが、いざ走らせてみると動きは良いし楽しいですよ~
納車が楽しみですね♪
勉強になります。
FFって前軸重が重いからか、一般に言われているアンダーを消すなら前下がり、とかリアバネを固く、とかが当てはまらない事も多い気がしています。
ターンインで鼻先の向きをすっと変えたいんですが、これがまた私には難しい・・・
リアを動かして曲げる、所謂リアステア自体を非効率的だとは思っていませんが、予めリアが動きやすいセッティングにする…つまり、リアステアありきなセッティングや操作を加える事が非効率的だと思っています。
そのいくつかの例が、前傾姿勢やリアバネのハイレート化、突っ込み重視で極端な荷重移動から生じるブレーキングドリフトのような進入スタイルなど、でしょうか。
ちなみに、鼻先を入れるような曲がり方は、初期操作で余計な事をしなければ、たぶん素直に曲がり始めるはずで、実際にウリさんのここ最近のヘアピンの曲がり方はそれに近い気がしますが(笑)